ミレーを中心に、他に6人の現役及び初心の画家たちが写っている写真を物語る
1856年ドーミエの奥さんがミレーの長男フランソワの代母になっているとあり、代父はルソー。この年の3月四女エミリーが生まれているので、一緒に長男と二女も洗礼を受けさせました。フランソワは既に七歳です。(1850年バルビゾンで生まれた三女マルガリットはこの年4月30日にフアルダン夫婦が代親で先に洗礼しています。想像ですが、四女の誕生祝に来たフアルダン夫婦に説得されて、先に三女の洗礼をしたのでしょう。その後、9月21日にサンシエ夫婦、ルソー夫婦、ドーミエ夫婦がバルビゾンで、代親として立会い三人の洗礼を行いました。)ミレーはそれに付いて「一緒にすれば洗礼代が安く済む」と言ったとか、それはいいとして、代親の件は、ドーミエとミレー、ルソーの親しい関係の証として記しておきます。当時、ドーミエはパリのサン・ルイ島のアパートの最上階にアトリエを持っていましたが、バルビゾンに遠出をしていたことが分かります。1860年シャリヴァリ紙(ドーミエが戯画を描いていた新聞)を解雇されたので、経済的に困窮、1863年モンマルトルに引越し、最終的にクリシー通りに落ち着き、既に親しい間柄が、改めてルソーのパリの隣人となります。1865年にドーミエは、サン・ルイ島での隣人で、夏に避暑に泊まりに行っていた、ノートル・ダム寺院の修復を請け負った彫刻家のジョフロワ=ドショーム(ドービニーの幼馴染。ミレーの弟は、ドーミエの口利きでノートル・ダムの改修工事に使ってもらいました。この修復設計はヴィオレ・ル・デュックがしています。)が移り住んだバルモンドワに家を借り、移り住みました。ルソーの晩年既に精神障害のあった奥さんを、ルソー没(バルビゾンで1867年)後にドーミエは面倒を見て、何とか精神病院に入れ、彼女はそこで亡くなります。ドーミエはシャリヴァリ紙に再雇用されますが、その後、盲目になりバルモンドワで亡くなりなりました。このバルモンドワの家を大家から追い出されそうになり、コローが家を買い取りドーミエにプレゼントしたエピソードが残されていますが、真相は定かではありません。晩年のドーミエを助けたのはコローとドビニーです。 | | 
サン・ルイ島のアパートの最上階のアトリエ

その表示板 |
当然最後のドーミエの展覧会をデュラン・リュエル画廊で企画したドショームもドーミエを援助したと思われ、バルモンドワの広場にドショームが彫ったドーミエの大理石肖像がひっそり建っていますが、特には語られません。コローはミレーと同じ1875年、ドービニーは1878年、ドーミエは1879年に亡くなり、ドーミエはバルモンドワの墓地に先ず葬られますが、生前コローとドビニーが眠るペール・ラシェーズの墓地の彼等の脇に葬られたいとの希望を持っていたので、カルジャとナダールが発起人となり、翌年に改葬されました。
墓地の様子を写した写真掲載します。
(左の写真)コロー(左)とドービニー(右)の墓。それぞれ銅像でわかると思います。(中の写真)中央のドーミエの墓の横全体。その後ろにコローとドービニーの銅像の後が見えます。(右の写真)ドーミエの墓。(2008/04/19、修正)最近修復されたので、読めなくなっていた文字が読め、間違いが判明したので修正します。銘文は(最初のDAUMIERと刻まれた名の下)ではなく、一番下に刻まれ、カルジャの選で、「人々よ、高潔の士、ドーミエここに眠る。偉大なる芸術家にして、偉大なる市民。」(小谷民菜氏訳)とあり、(写真の中央部ですが、現在ほとんど読めなくなっています)は写真は中央部だけで、銘文は写っていません。(その下に)はドーミエの名前の下に夫人の名前が刻まれています。と修正します。2008年はドーミエ生誕200年に当たり修復されたようで、銘文の刻まれた場所(一番下)がわかり、修正いたします。文献に現在ほとんど読めなくなっているとあったので、最初から判読する努力を怠り、勝手に、読めなくなっていたドーミエの名前の直ぐ下に銘文が刻まれていたと思い込み、そう書きました。1895年まで存命した未亡人の名を刻む場所を残して墓碑がつくられることを知らなかったので、消えかかっていたドーミエの生没年代と場所が刻まれていた部分を銘文の記されていた部分と思い込んでしまいました。無知なるが故の思い込みを反省いたします。そして、ふと、この写真に出会ったときにミレーかもしれないと思い込み込んだことに始まるこのHPが思い込みに過ぎないで終わらせない努力を改めてしなければと思いました。
バルビゾン村にこだわって調査をするといいながら、バルビゾンからも、「写真」からも離れて、個人的感傷に浸りましたが、どうしても語りたい事の一つなので、お許しください。ミレーもオーヴェルニュのドービニーの家に遊びに行くので、ドーミエにそこで会いたいと手紙を書いている事を付け加えておきます。
ついでと言っては、彼に悪いですが、ナダールはミレーのところで語り、別テキスト略伝を付けましたので、ドーミエを崇拝し、墓移転の発起人で、詩を書き、戯曲を書き、役者にもなり、カリカチュールも描く、写真家のカルジャについて、多分バルビゾンにもミレーやルソー以外にも多くの画家がいたはずですが、名も残らず、忘れられてしまっていると思われ、そんな彼ら同様に、当時活躍した割にはあまり知られていないカルジャに関して、少しだけ語りたいと思います。
カルジャは1828年アン県(ローン県、リヨンが県庁所在地の隣の県)に生まれ、10歳の時家族と共にパリに出てきて、母親が絨毯と絹織物製造業者の家の管理人をやっていた関係で、そこのデザインを引き受けていたヘンリーと言うデザイナーに13歳の時徒弟奉公を認められ、3年間勤めます。1848年の七月革命の時、短期間、同業組合から代表として送られ、国民軍の中尉になったとあり、共和制の志向がこの時はっきり表れ、その後変わることがなかったと言うことで、引き続き、商業デザイナーの道を歩いていたのでしょうが、演劇への嗜好が嵩じて、脚本を書き、自ら演じるようになりますが、商業的に成功せず、しかし、役者の立場で知り合った人たちを、大きな頭に小さな体にして描いたカリカチュール「町の劇場」で成功し、戯画家になり、ナダール同様、写真にも興味を持ち、写真家ピエール・プティ(カルジャはピエール・プティの戯画肖像を描いています。)に師事し、多くの著名人の肖像写真を残しています。自身詩を書き、詩の会合で、不手際を演じた(詩を朗読できなかった)ランボーを罵倒したため、会合後にランボーに待ち伏せされ傷を負う事件などありましたが、ユーゴーに詩を書き送る位で、ユーゴー、ボードレール、ランボーの有名な肖像写真は彼の手になります。彼の写真スタジオはラフィット通り58番地の中庭にあり、そこでサロン(晩餐会)を主宰したり、写真や詩の他に、共和主義者として石版画付き週刊新聞「ブールバード」紙を発行し、そこにドーミエの石版画を掲載したりしましたが、ナポレオン三世とは折り合わず、政府の圧力を感じ、週刊新聞を自主廃刊し、それにより大きな借財を負いました。ガンベッタを後援し、パリコミューンの兵士の貴重な写真を残しますが(この写真が後に国民政府のコミューン狩りに利用されたのかもしれません。となるとそのことでカルジャの評判はかなり悪くなるでしょう。但し、文献に書かれている訳ではなく、私的憶測です)、帝制崩壊後の第三共和制の下では破産同然で、活躍の場もなく、過去の写真の焼き直し展覧会で糊口を潤していたようですが、撮影した多くの著名人の肖像写真の版権問題も写真館の元共同経営者との争いになり、政財界人(ロスチャイルド)との絡みでも問題があり、明らかにされない部分が多々あるようです。一時期パリの社交界で活躍した割には、知られていない写真家は1906年に亡くなり、写真ネガを相続した娘は、母親の跡を継ぎ、女優をしていたようで、写真ネガは完全に保存はされず、大きな版はほとんど割られ、10枚ほどが残されたとか、後は推して知るべきでしょう。1980年にニエプス写真美術館で開催された「カルジャ」展が最初の総合的な企画展のようで、その後、同じ学芸員により、パリのカルナヴァレ美術館で「カルジャ」展がありましたが、それ以後取り上げられていないようです。興味のある人は調べてみたら、ナダール同様、文化の変換期が生む多芸な才人の姿が現れるかもしれません。 | | 
ジルによるカルジャの戯画

カルジャ作プティ

プティの宣伝写真。右後ろのカルジャの戯画は実素描なので石版と画像が反転か?鏡に映した映像を写真にしているのか? |
.............. 長い寄り道をしましたが、いよいよ撮影場所の確証に迫ります。
そうこうする内に、「写真」の背景の建物の窓から顔を出している二人とよく似た人物の肖像画を、偶然にバルビゾンの写真集を眺めていて見つけました。将に天啓という感じがし、そこに書かれている、シャイイ・エン・ビエールの旅籠屋シュバル・ブロンを調べることにしました。
バルビゾンに関しては書きたいことがまだありますが、後にして、今回の最重要項目、バルビゾンの隣村、というより、元々バルビゾンは村にもなっていず、とくると、最初に「写真」を見た時に頭に浮かんだミレーのデッサンが口絵になっていた、ミレーを云々する人の何人かは必ず読んでいるであろう岩波文庫「ミレー」ロマン・ロラン著、蛯原徳夫訳に登場願います。(シャイイに下線付加)
第3章、バルビゾンにおけるミレー、 より
バルビゾンは当時ヒースや森に埋もれた小部落で、ほとんど村にもなっておらず、教会もなければ墓地もなく、郵便局もなければ学校もなく、市場も商売屋も――宿屋さえもなく、すべてのものを隣村のシャイイから仰がねばならなかった。そこを訪れるものといえば、当時まだ無名の数人の画家ばかりであった。そして住民はみなごく貧しい樵夫か農夫であった。
この記述でもわかるように、元々この地域ではシャイイのほうが開けていて、行政区画もバルビゾンはシャイイに含まれていましたが、1903年11月26日に独立して、バルビゾン村になりました。シャイイ村の住人は1000人、バルビゾン村は300人以下、シャイイの旅籠屋シュバル・ブロンが郵便の中継地であったとあり、当時、乗合馬車が郵便物を運んでいたので、シュバル・ブロンが宿場駅であったわけで、シャイイがこの地域の中心であり、旅籠屋シュバル・ブロンが重要な役割をになっていたことがわかります。ジャックとミレーが最初にバルビゾンを訪ねた時、この乗合馬車でパリからシャイイまで来て、そこから歩いてバルビゾンに行きました。そして、バルビゾン派の画家、特にミレーにより、何時ごろからか、バルビゾン村のほうが有名になってしまい、シャイイ村はさびれて行きます。しかし、ミレーもルソーも、加えてサンシエもシャイイの教会近くの墓地に葬られていることから、当時を偲べると思います。
このホームページの第一章 ミレーが写っていると思われる写真の発見 の「ミレーについて」にリンクすれば三人の墓の写真を見られますが、そのページに飛ばない人がいるかもしれないので、ここにも掲載します。
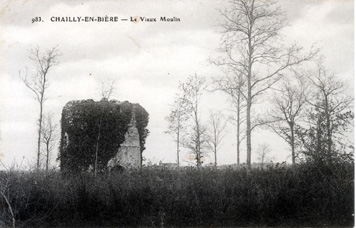
シャイイ平原の古い粉引き風車 | 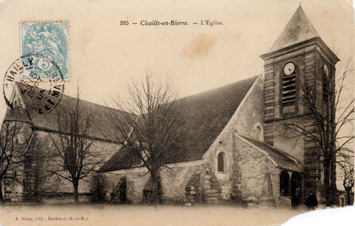
シャイイの教会 |
ミレーはこのシャイイ平原の粉引き風車を遠景にして画を描いています。この絵葉書の中央、遠くに小さくシャイイの教会が見えるのが分かりますか? 「晩鐘」はこのシャイイの教会の鐘の音です。ミレーが想を練りながらこのあたりを歩き回っていた雰囲気を感じられないでしょうか?

ルソーの墓 | 
ミレーの墓 | 
ミレーとルソーの墓 | 
サンシエの墓 |
・ サンシエの墓の向こうに見える丸く刈り込んだ植木のある場所がルソーとミレーの墓(3番目の写真)です。
どんな形で見せたら効果的かと考えてみましたが、特別に身構えて、変に前置き(既に充分な序章をつけましたが)を書かない方がよいと思うので、素直に掲載します。
尚、夫婦の肖像画は本からのコピーで、その後、図書館で再度探しましたが見つからず、何年の出版か確認できず、著作権の有無に関して明確ではありませんが、写真自体はかなり昔に撮影されたものと思われます。何故なら、この肖像画を直接独立した形で見ているので、部屋は現状を維持されていないので、基本的には著作権は消滅していると思われます。
 旅籠屋シュバル・ブロンの部屋の戸板に描かれた主人夫婦の肖像画
旅籠屋シュバル・ブロンの部屋の戸板に描かれた主人夫婦の肖像画
 「写真」の背景の窓から顔を出している夫婦
「写真」の背景の窓から顔を出している夫婦
フォンテーヌブローの森に写生に来て、旅籠屋シュバル・ブランに泊まった画家が戸板に描いて行った旅籠屋夫婦の肖像が、この二人の肖像写真の人物と思われますか?
この
「写真」の撮影場所が、バルビゾン村の隣、シャイイ村の旅籠屋シュバル・ブロンの前となれば、
「写真」の中の顔の長い、ノルマンディー人の顔の特徴を持つ人物が、ミレーである確証にまた一歩近づいたと思われますが、いかがお考えでしょうか?
今回は、この決定的とも思える、旅籠屋シュバル・ブロンのパイヤール夫婦の肖像画発見で、終了します。改めて、この「写真」の中のミレーと査定した人物と共に、再検討して、観比べてください。
○ 再掲載しますので、再確認してください。
上の写真は本からコピーしたものですが、かっての旅籠屋シュバル・ブロンの部屋です。何年の撮影かも撮影者も不明です。かなり以前に撮影されたものとして、著作権は失効していると判断して、読者に資するため、転載させていただきます。
いかがですか? かなり重要、且つ、決定的なので、縦だけではなく、横並べの比較も掲載します。ミレーとこの夫婦で、発見した「写真」がかなり貴重なものであることが証明されつつあることを信じていただけますか?
しかし、この二人をパイヤール夫婦と査定できた後は、当然、撮影場所は旅籠屋の前。楽勝。万歳!とはいきませんでした。以下次回。乞うご期待!
著作権について 著作権に関しては充分配慮していますが、万が一著作権に抵触する場合、著作権者のご要望があれば即座に削除いたしますのでメールにてお知らせください。このサイトは、偶然見つけた写真に写っている人物を如何に査定したかを物語ったもので、どうしても画像による説明が必要になります。営利を目的に画像を使用しているわけではない点を著作権者様にご理解をいただき、掲載許可をいただけたら幸いです。また、読者の皆様におかれましては、著作権に充分のご配慮をいただき、商用利用等、不正な引用はご遠慮くださいますよう、よろしくお願いいたします。